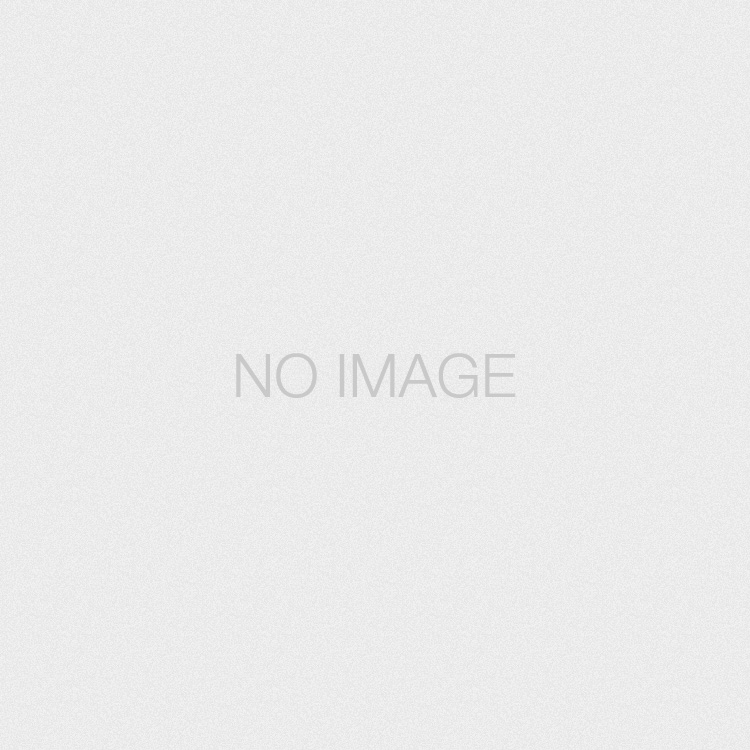2018年11月25日
ELNO H-295A

また記憶の曖昧なおじいちゃんみたいに同じものを買う……
よく知られたELNO H-295Aですね。今回はケーブルとのセットです。

以前買ったもの(→)と同じものですね。
左右組み換え可能なんですが今回のは来たまま右側用にしています。

イヤカップカバーも付属してました。遮音用でしょうかね。

すっと嵌める感じです。蒸れそう。

今回本命のケーブル類。SEM52SL用のNF10コネクタとPTTスイッチです。
TK5でも同じこと思いましたがPTTのケーブルこんなに細くて大丈夫なのか。

おなじみ(?)LEMOコネクタです。SEM接続用は5ピン。

PTT接続用は2ピンでした。

LEMOといえば自動ロック付の高級コネクタなわけですが、
どうしても華奢な印象で付け外しに慎重になっちゃいますね。

おまけ感覚で付いてきたキットバッグ。本当にこのバッグで支給されるんでしょうか。

PTTはケーブルを遡上して本体にくっ付いていることも。
パラシュート補修テープでまとめるといかにもな雰囲気に。

FschJgBtl313の2010年派遣チームから。828ヘルムとの組み合わせが個人的にお気に入り。

FschJgBtl373の2010年派遣チームから。
ヘッドバンドが置き換えられていますが、本当に使いにくいんですよ。
奥側の人に至ってはイヤカップまで外しちゃってます。
もともとモノがあまり品質よくなさそうなんですよね……

イヤーカップの様子がわかります。PTTはH-267用でもう無茶苦茶。
Tschüs!!
タグ :ELNO
2018年11月10日
Operation Libelle
今回はドイツ連邦軍陸上部隊による初の銃撃戦に関する内容です。
諸兄の皆さまは「99年のプリズレンの事件は以前取り上げただろう!!」とお怒りのことでしょうが、
プリズレンの場合は正確に言うと「初めて銃撃戦による殺害が認められた」事件だったんですね。
私も最近まで知りませんでした……
(プリズレンの記事はこちら→「血の日曜日」)
史上初、というものは得てして曖昧さを含むものですが、BWファンとしてこの間違いはお恥ずかしい。
ということでリベンジも兼ねて(?)、今回は97年にアルバニアで行われた民間人救出作戦を取り上げます。
作戦名は「Operation Libelle(リベレ)」、Libelleはドイツ語でトンボを意味する語ですね。

さて時代背景であるところの「アルバニア暴動(1997年)」は、簡単に言えばアルバニアの経済破綻を発端とした全国各地の大規模な暴動のこと。
治安が悪化していくと共に内戦状態、無政府化にまで陥り、最終的には国連軍が派遣され治安回復作戦を実行するまでに至りました。
暴動が端を発したのは97年の1月のこと。3月2日には大統領によって非常事態宣言が発令され、遅れて同月11日に外国人の退去命令が下されます。
退去命令と前後して米軍やイタリア軍は空港からの避難作戦を行っており、この時点ではまだアルバニア政府がある程度機能していたようですが、
暴動・鎮圧がさらに激化した3月13日にはもはやドイツ大使館に逃れた数十名の避難民を、チャーター便で脱出させる手段は失われていました。
作戦前夜となる3月13日、この事態を重く見た時の国防大臣フォルカー・リューエがドイツ連邦軍によるドイツ人救出作戦の発動を決定します。
このときアルバニア政府への通達などは行われなかったようです。すでに政府がほとんど機能していなかったということなのかもしれません。
早い段階で海軍のフリゲート艦「ニーダーザクセン(F208)」が作戦のバックアップのためアルバニアのドゥラス(Durrës)港に進入しました。
ドゥラス港はドイツ大使館のある首都ティラナ(Tirana)と目と鼻の先です(といっても交通路で30kmほどの距離)。
さらに作戦当日、3月14日の朝、SFOR任務のためにボスニア・ヘルツェゴビナのライロバッツ(Rajlovac)キャンプに配備されていた6機のCH-53Gが、
クルーおよび装甲擲弾兵部隊・医療部隊の計89名からなるタスクフォースを伴ってクロアチアの最南端の街ドゥブロヴニク(Dubrovnik)へ移動します。
このときドイツ国内では3機のC-160が24名の兵士(6名の衛生兵含む)と共にランツベルク/レッヒ航空基地で待機していました。
ランツベルク/レッヒといえば当時第61空輸航空隊(LTG61)が詰めていた基地ですが、LTG63もこの作戦に参画していたようです。

ざっくり地図(D-Mapsより)
ヘリ部隊は午後にはモンテネグロのポドゴリツァ(Podgorica)に移動。
さらに待機していたC-160がポドゴリツァを目指して離陸。
さて、避難民のピックアップポイントに選ばれたのはティラナ国際空港、ではなくドイツ大使館のあるティラナ中心部に近い「ラプラカ飛行場」。
ほとんど使われなくなっていた飛行場ですが大使館から3kmほどの距離にあり、大通りで結ばれているこちらの方が好都合だったのでしょう。
このとき避難民は主に車両で移動したと思われます。飛行場までの移動の段階からドイツ側の誘導、手引きがあったのではないでしょうか。
(ちなみに大使館からティラナ国際空港までは12kmほどあります)
15時40分、タスクフォースがティラナのラプラカ飛行場に到着しました。
このとき別の避難作業に当たっていた米軍のブラックホークが銃撃され引き返すという事件が起こっていたにもかかわらず、
作戦の指揮を執っていたSFOR指揮官Henning Glawatz大佐(当時)は作戦の続行を決定しています。
(この時点でピックアップポイント周辺はほぼ内戦状態であったことがうかがえます)
着陸したCH-53Gから兵士たちが展開し飛行場の安全を確保、避難民の収容作業を始めたわけですが、兵士による銃撃戦はこの過程で勃発しました。
襲撃者は不明ということになっていますが装甲車を伴っていたということですので、武装した暴徒というより民兵や反乱軍だったのではないかと思います。

G36はまだ配備されていないので連邦兵士の武装はG3です。アーマーはブリストルで、S95(S88?)を併用しています。

MG3も展開。関連写真を見るとPzFst3らしきものも写ってますので対装甲戦闘も想定されていたんでしょうか。
CH-53Gが1機破損のほかアルバニア人避難民1名が負傷という結果に。ただし無事収容を済ませているので追い払うことは出来たのでしょう。
16時9分、ドイツ人21名、日本人13名を含む総勢98名にのぼる民間人の収容に成功します(ソースによって104名とも言われております)。
避難民はポドゴリツァで下され(少なくともドイツ人は)ケルン・ボン空港まで移送されました。
ニュース映像よりライロバッツに帰投したタスクフォース。
ヘリ部隊(mTrspHubschrRgt 25 & HFlgRgt 35)のワッペンが確認できます。
その後の処理によると銃撃戦では総計188発の銃弾を発砲していたとのこと。襲撃者の死亡者、負傷者は不明のままとなっています。
翌月、国連軍による安定化作戦「オペレーション・サンライズ」が展開され、ようやく騒動が終結へ向かうこととなりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
連邦軍による民間人収容作戦ということで以前取り上げた「オペレーション・ペガサス」との類似点・相違点も興味深いものです。
時間的にも航続距離的にも、また収容人数的にもなるべく(リビアのおように)C-160のような固定翼機を現地に派遣したいところでしょう。
この場合はSFORで派遣されていたヘリ航空隊が利用できたわけですが、そうでなければティラナ国際空港にC-160を強行着陸でしょうか?
あるいはニーダーザクセンから歩兵部隊が上陸し(ティラナとドゥラスは幹線道路で結ばれていますので)陸路を伝って収容していたかもしれません。
ドイツはアルバニアやリビア以外でも在外ドイツ人の避難作戦を行っています(ウクライナ、南スーダンなど)。
これらの場合は武装を伴わない状態での航空機派遣・避難誘導など、ある程度外交的な作戦かと思われます。
計画のみで最終的には実行されなかった作戦もいくつか知られており(イエメン、イラク、ザンビアなど)、
ドイツ政府・ドイツ連邦軍がこうした緊急事態への備えを常に維持しているということがわかります。
94年のルワンダでは政治的懸念からドイツ人救出をベルギー軍に頼らざるを得なかったという背景もありますので、
97年アルバニアのオペレーション・リベレはドイツ連邦軍としても大きな転換点であると捉えることが出来そうです。
法的にはまだ色々問題があるそうですが、民間人避難・救出は軍隊の大事な役割の一つと言えるでしょう。
Tschüs!!
諸兄の皆さまは「99年のプリズレンの事件は以前取り上げただろう!!」とお怒りのことでしょうが、
プリズレンの場合は正確に言うと「初めて銃撃戦による殺害が認められた」事件だったんですね。
私も最近まで知りませんでした……
(プリズレンの記事はこちら→「血の日曜日」)
史上初、というものは得てして曖昧さを含むものですが、BWファンとしてこの間違いはお恥ずかしい。
ということでリベンジも兼ねて(?)、今回は97年にアルバニアで行われた民間人救出作戦を取り上げます。
作戦名は「Operation Libelle(リベレ)」、Libelleはドイツ語でトンボを意味する語ですね。

さて時代背景であるところの「アルバニア暴動(1997年)」は、簡単に言えばアルバニアの経済破綻を発端とした全国各地の大規模な暴動のこと。
治安が悪化していくと共に内戦状態、無政府化にまで陥り、最終的には国連軍が派遣され治安回復作戦を実行するまでに至りました。
暴動が端を発したのは97年の1月のこと。3月2日には大統領によって非常事態宣言が発令され、遅れて同月11日に外国人の退去命令が下されます。
退去命令と前後して米軍やイタリア軍は空港からの避難作戦を行っており、この時点ではまだアルバニア政府がある程度機能していたようですが、
暴動・鎮圧がさらに激化した3月13日にはもはやドイツ大使館に逃れた数十名の避難民を、チャーター便で脱出させる手段は失われていました。
作戦前夜となる3月13日、この事態を重く見た時の国防大臣フォルカー・リューエがドイツ連邦軍によるドイツ人救出作戦の発動を決定します。
このときアルバニア政府への通達などは行われなかったようです。すでに政府がほとんど機能していなかったということなのかもしれません。
早い段階で海軍のフリゲート艦「ニーダーザクセン(F208)」が作戦のバックアップのためアルバニアのドゥラス(Durrës)港に進入しました。
ドゥラス港はドイツ大使館のある首都ティラナ(Tirana)と目と鼻の先です(といっても交通路で30kmほどの距離)。
さらに作戦当日、3月14日の朝、SFOR任務のためにボスニア・ヘルツェゴビナのライロバッツ(Rajlovac)キャンプに配備されていた6機のCH-53Gが、
クルーおよび装甲擲弾兵部隊・医療部隊の計89名からなるタスクフォースを伴ってクロアチアの最南端の街ドゥブロヴニク(Dubrovnik)へ移動します。
このときドイツ国内では3機のC-160が24名の兵士(6名の衛生兵含む)と共にランツベルク/レッヒ航空基地で待機していました。
ランツベルク/レッヒといえば当時第61空輸航空隊(LTG61)が詰めていた基地ですが、LTG63もこの作戦に参画していたようです。

ざっくり地図(D-Mapsより)
ヘリ部隊は午後にはモンテネグロのポドゴリツァ(Podgorica)に移動。
さらに待機していたC-160がポドゴリツァを目指して離陸。
さて、避難民のピックアップポイントに選ばれたのはティラナ国際空港、ではなくドイツ大使館のあるティラナ中心部に近い「ラプラカ飛行場」。
ほとんど使われなくなっていた飛行場ですが大使館から3kmほどの距離にあり、大通りで結ばれているこちらの方が好都合だったのでしょう。
このとき避難民は主に車両で移動したと思われます。飛行場までの移動の段階からドイツ側の誘導、手引きがあったのではないでしょうか。
(ちなみに大使館からティラナ国際空港までは12kmほどあります)
15時40分、タスクフォースがティラナのラプラカ飛行場に到着しました。
このとき別の避難作業に当たっていた米軍のブラックホークが銃撃され引き返すという事件が起こっていたにもかかわらず、
作戦の指揮を執っていたSFOR指揮官Henning Glawatz大佐(当時)は作戦の続行を決定しています。
(この時点でピックアップポイント周辺はほぼ内戦状態であったことがうかがえます)
着陸したCH-53Gから兵士たちが展開し飛行場の安全を確保、避難民の収容作業を始めたわけですが、兵士による銃撃戦はこの過程で勃発しました。
襲撃者は不明ということになっていますが装甲車を伴っていたということですので、武装した暴徒というより民兵や反乱軍だったのではないかと思います。

G36はまだ配備されていないので連邦兵士の武装はG3です。アーマーはブリストルで、S95(S88?)を併用しています。

MG3も展開。関連写真を見るとPzFst3らしきものも写ってますので対装甲戦闘も想定されていたんでしょうか。
CH-53Gが1機破損のほかアルバニア人避難民1名が負傷という結果に。ただし無事収容を済ませているので追い払うことは出来たのでしょう。
16時9分、ドイツ人21名、日本人13名を含む総勢98名にのぼる民間人の収容に成功します(ソースによって104名とも言われております)。
避難民はポドゴリツァで下され(少なくともドイツ人は)ケルン・ボン空港まで移送されました。
ニュース映像よりライロバッツに帰投したタスクフォース。
ヘリ部隊(mTrspHubschrRgt 25 & HFlgRgt 35)のワッペンが確認できます。
その後の処理によると銃撃戦では総計188発の銃弾を発砲していたとのこと。襲撃者の死亡者、負傷者は不明のままとなっています。
翌月、国連軍による安定化作戦「オペレーション・サンライズ」が展開され、ようやく騒動が終結へ向かうこととなりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
連邦軍による民間人収容作戦ということで以前取り上げた「オペレーション・ペガサス」との類似点・相違点も興味深いものです。
時間的にも航続距離的にも、また収容人数的にもなるべく(リビアのおように)C-160のような固定翼機を現地に派遣したいところでしょう。
この場合はSFORで派遣されていたヘリ航空隊が利用できたわけですが、そうでなければティラナ国際空港にC-160を強行着陸でしょうか?
あるいはニーダーザクセンから歩兵部隊が上陸し(ティラナとドゥラスは幹線道路で結ばれていますので)陸路を伝って収容していたかもしれません。
ドイツはアルバニアやリビア以外でも在外ドイツ人の避難作戦を行っています(ウクライナ、南スーダンなど)。
これらの場合は武装を伴わない状態での航空機派遣・避難誘導など、ある程度外交的な作戦かと思われます。
計画のみで最終的には実行されなかった作戦もいくつか知られており(イエメン、イラク、ザンビアなど)、
ドイツ政府・ドイツ連邦軍がこうした緊急事態への備えを常に維持しているということがわかります。
94年のルワンダでは政治的懸念からドイツ人救出をベルギー軍に頼らざるを得なかったという背景もありますので、
97年アルバニアのオペレーション・リベレはドイツ連邦軍としても大きな転換点であると捉えることが出来そうです。
法的にはまだ色々問題があるそうですが、民間人避難・救出は軍隊の大事な役割の一つと言えるでしょう。
Tschüs!!